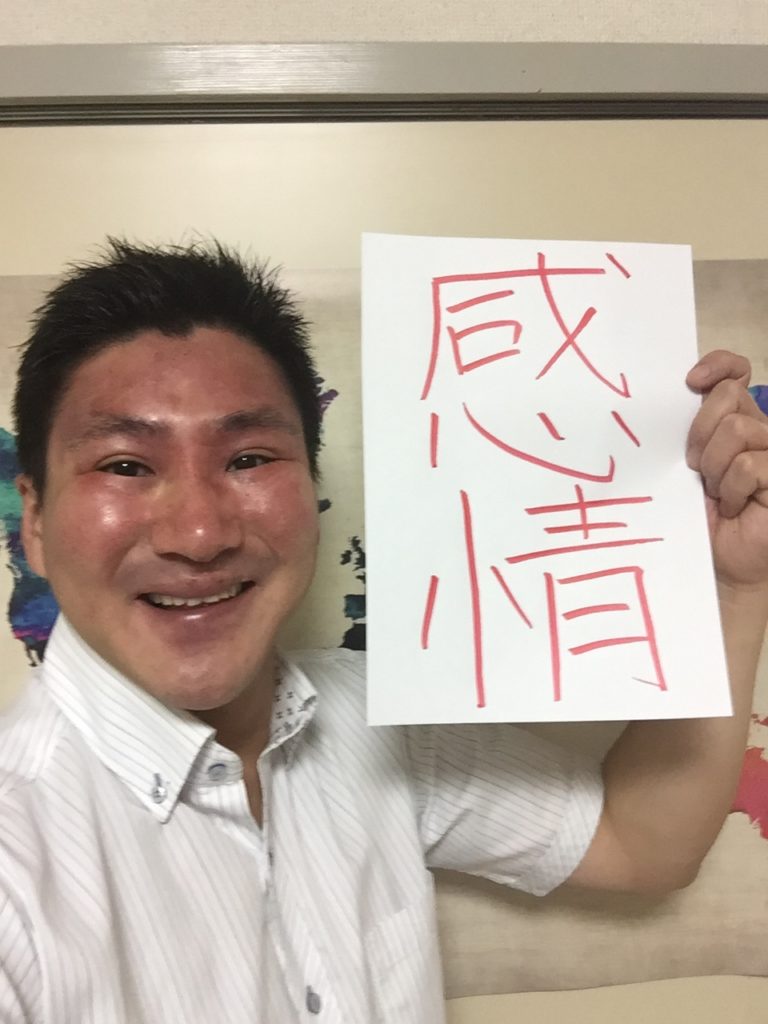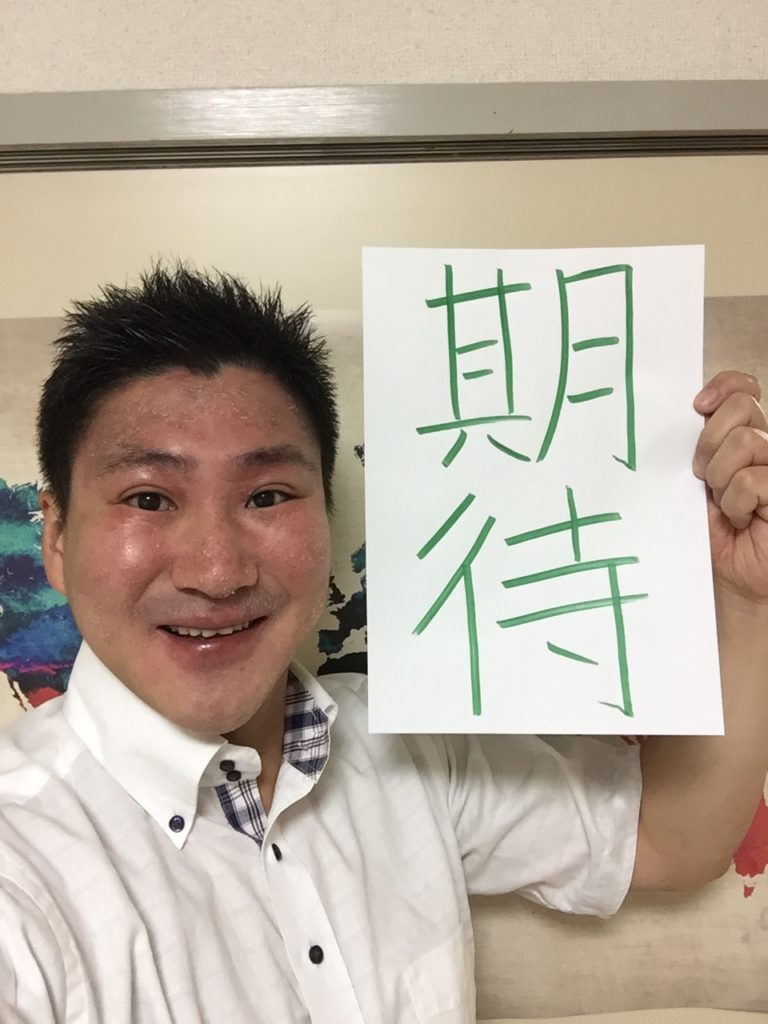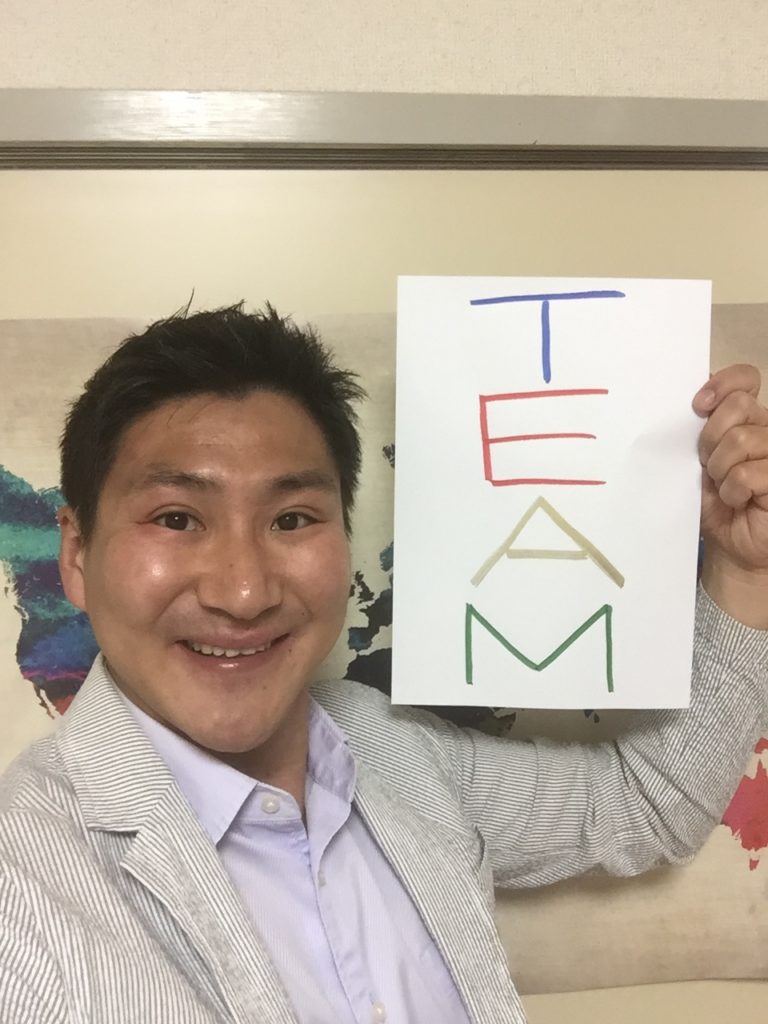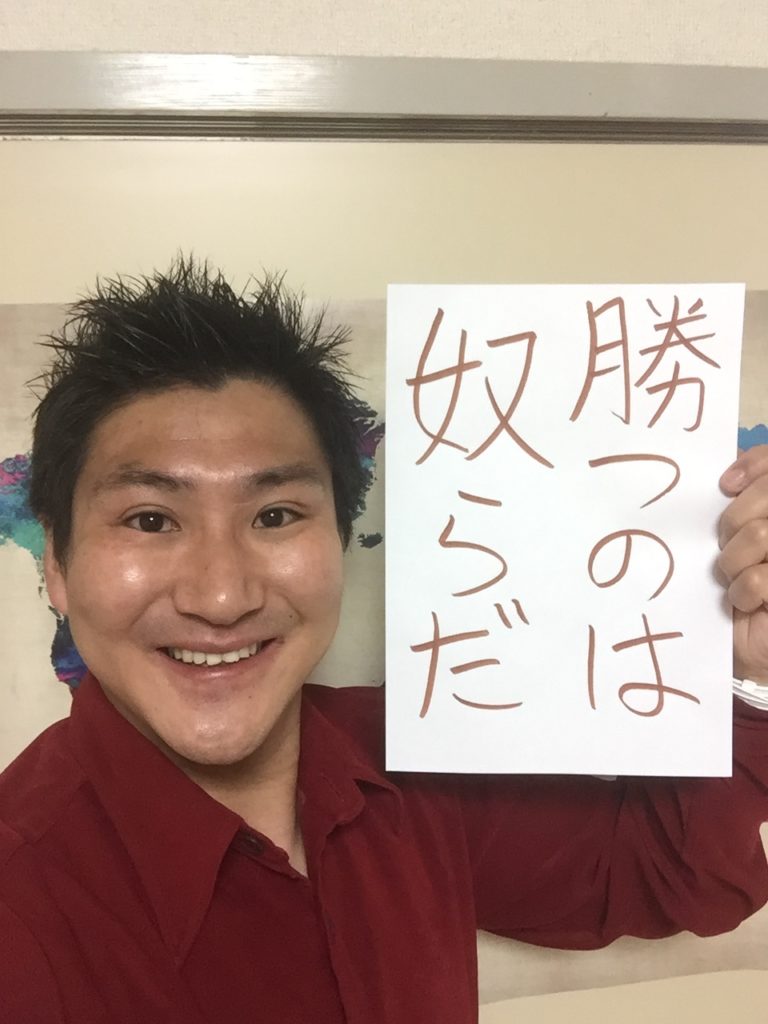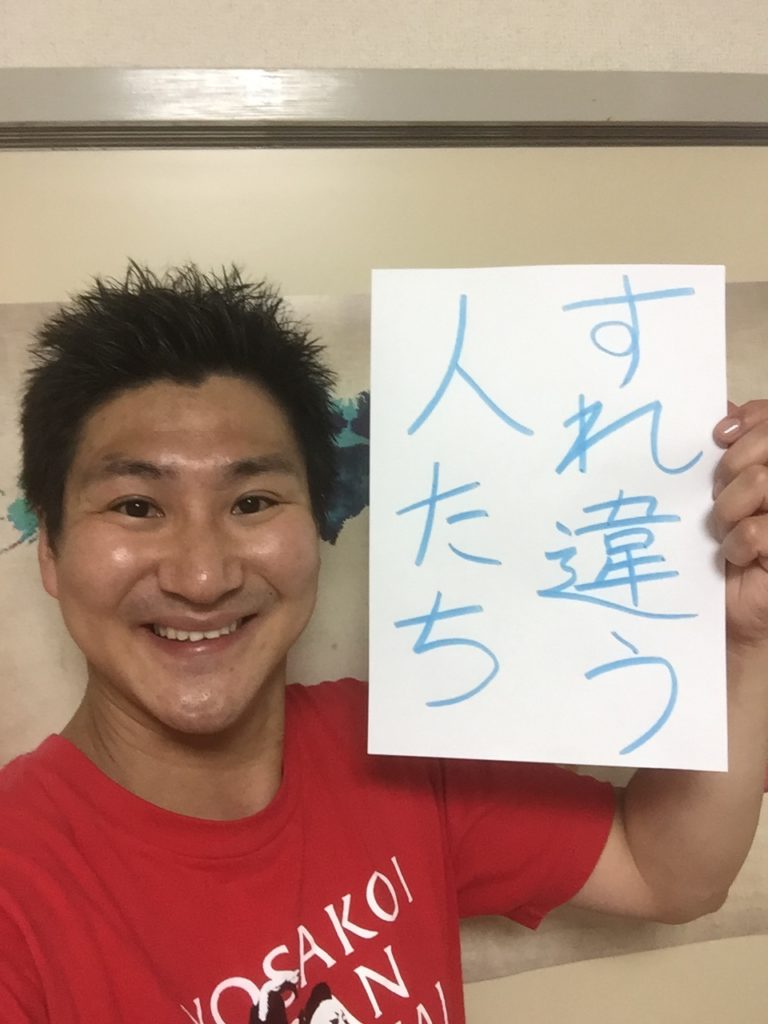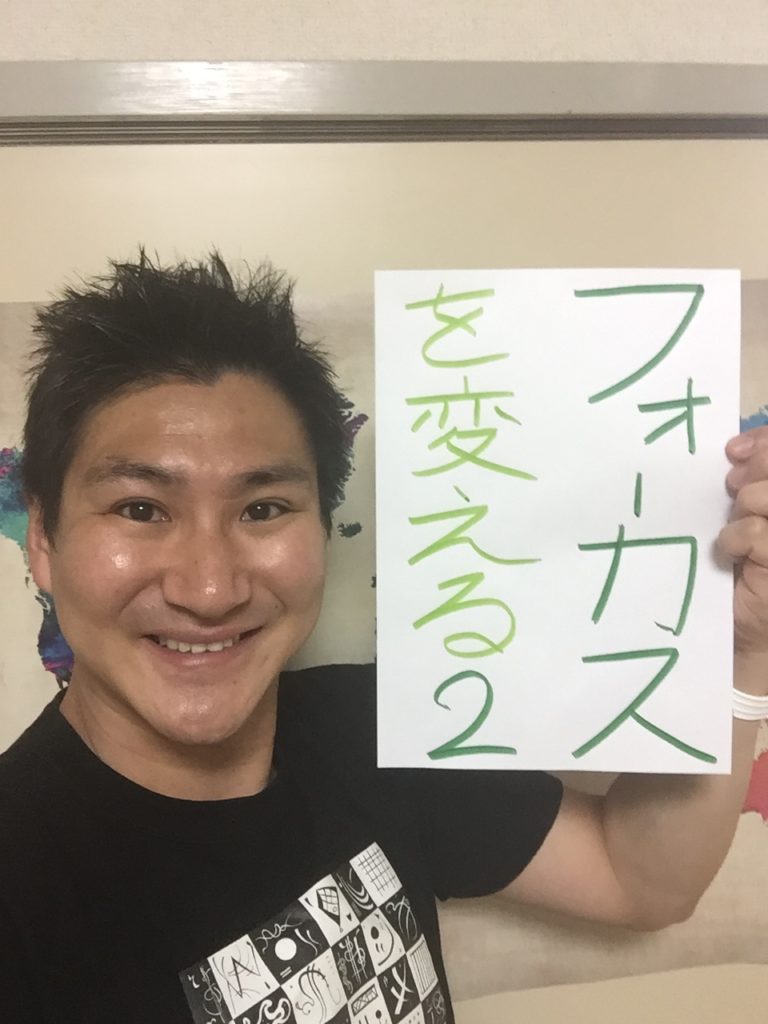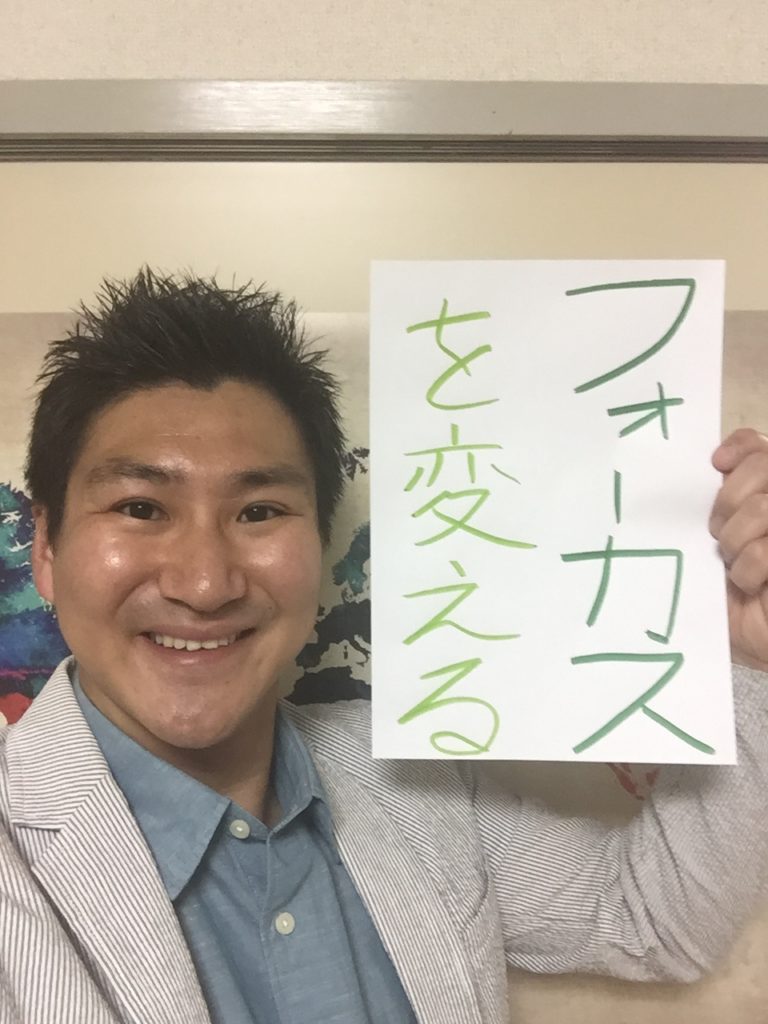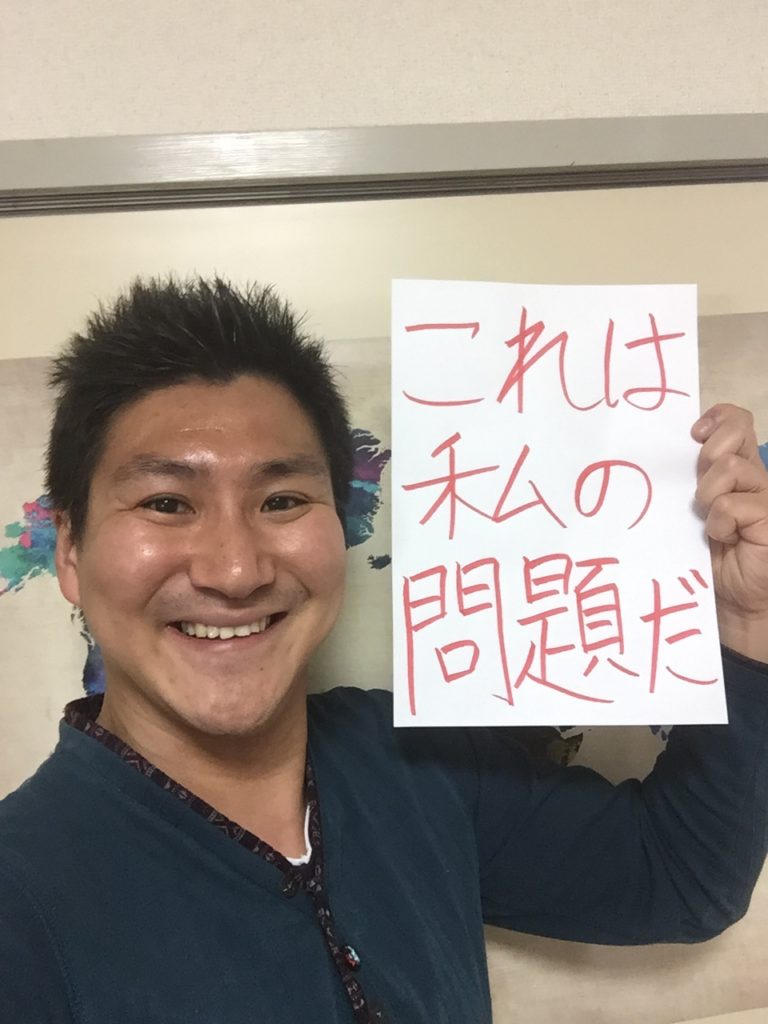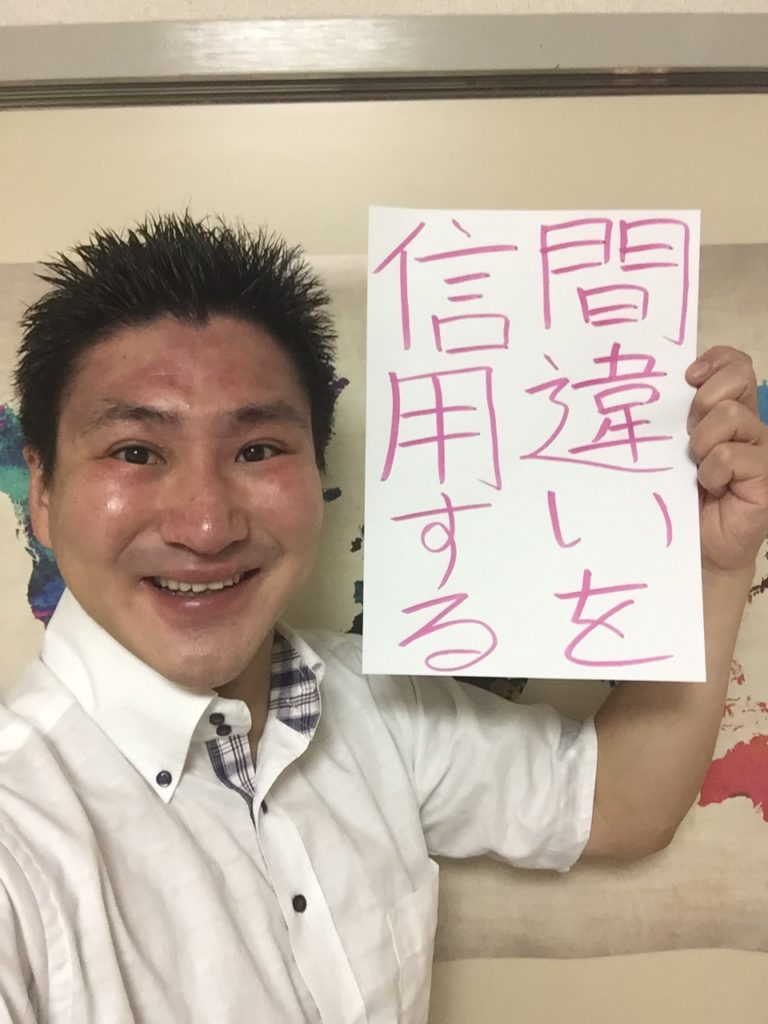
「間違いを犯さない者を信用してはならない」ピーター・ドラッカーの言葉で、深く突き刺さった一言。最初読んだとき、どういうことだろう?と思った。間違える人は信用出来ないんではなくて?でも前提が違った。
人は必ず間違いを犯すもの。
もし間違いをしていないなら、
その者は何もやっていない。
盗塁王は盗塁の失敗数も最大
である。という話を
聞いたことがある。
出来る営業マンほど
断られる件数や
始末書の数が多いとも。
この言葉を知ってから
ミスや間違いを犯した人に対して
責めるのではなく
行動した人なのだと
思えるようになった。
何もやらない人よりも
やって失敗をした人こそ
信用しよう。